多分ほとんどの方が一度は耳にした事があるフレミングの左手の法則、その法則を利用した構造のスピーカーです。一般的にテレビ、オーディオ機器、また通勤時皆さんがご利用しているイヤホン等、この構造のスピーカーの市場調査を特にしたわけでは在りませんが、この業界に居る私の目から見て恐らく、全世界の50%以上(多分それ以上)がこのタイプのスピーカーだと思います。優れている性能を有している構造だけに、それほど普及しているという事です。
この構造を組み立てる上では、大半が部品糊付け工程になり、寸法サイズも様々だけに大量生産といえども、なかなか自動化が難しく、現在では特殊仕様を省いて恐らく90%以上が人件費の安い国で製造していると言うのが実情です。
この様な状況を考えると、この先の将来はと・・・、考えてしまう事がありますが。
フレミングの左手の法則(John Ambrose Fleming 1849〜1945)
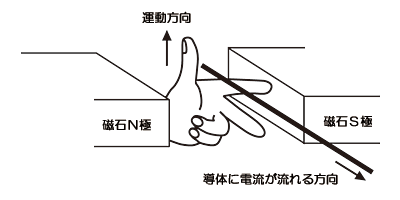
- 人指し指は、磁石のN極からS極へ走る磁束方向を示し、
- そこへ磁束に対し直交する様に導体を置き、中指の示す方向に電流を導体に流すと
- 親指は、導体の運動方向を示します
フレミングの左手の法則を用いた実際の構造
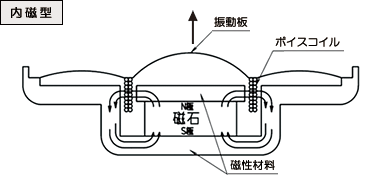
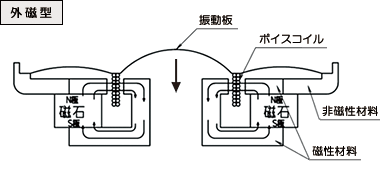 |
内磁型、外磁型の磁気回路を持った構造2点を示しました。
共に磁石のN極からS極へ流れる磁束の通り道を磁性材料で構成しています。
その磁束の通り道に間隙を作りそこへボイスコイルを位置させます(図では2層巻きのコイル)
この断面図でドット方向へ電流を流すと上記フレミングの左手の法則に従い矢印方向の運動がボイスコイルに伝わり、ボイスは振動板に固定されている為、振動板の動きが矢印方向に現れます。 |
この構造の運動力は以下の式により表されます。
| F=B・I・L |
F |
: 運動力(単位 N) |
| B |
: ボイスコイルが位置する間隙の磁束密度(単位 Wb/m2) |
| I |
: ボイスコイルに流れる電流(単位 A) |
| L |
: 磁束と直交するボイスコイル長(単位 m) |
以前、振動板のコンプライアンスを測定出来ないかと、何とか測定器を作成し、興味半分でその測定器を利用し、この運動式の通りの運動を行っているのか測定したところ、かなりの精度でこの運動式が適用できると確認した記憶があります。(余談でした)
この構造で、変換効率を上げるには式のとおり要素は3つ(B、I、L)しか在りません。
電流を上げれば、運動力は単純に上がりますがそれでは変換効率が上がったとは言えませんので
B(磁束密度)、L(磁束と直交するボイスコイル長)この2つです。
Lを長くすると電気的なインピーダンスが上がってしまいます。もしHiFiとしての検討でしたら振動板を実質重くしてしまった内容になってしまうので、最終的にはBを何とかして上げると言う事になってしまいます。
ボイスコイルを位置させる間隙の間隔を狭くすると、磁束は距離の2乗に反比例すると言われていますので、効果を期待できるのですが、ボイスコイルが入らないとこの構造が成立しないと言う事になり限度があります。最終的には磁石のパワーに依存する内容になってしまいます。
変換効率を上げると言う事は、簡単な話、磁石メーカーさんの開発次第と言う事になってしまいます。
優等生の構造でも、変換効率の内容になると、ちょっとした欠点もあるのですね。
ヘッドホーンに使用されるダイナミック型スピーカの筐体に関して
振動板はHiコンプライアンス(剛性が低い)の材料を一般的に使用しています。
その為、fo(スピーカーの共振周波数)を低く取る事が出来ます、また筐体で音響インピーダンスを上げては
持ち前のfoを高い周波数に上げてしまう為、音響インピーダンスを上げないような構造を取ります。
例:一度は聞いたことが在ると思いますが、オープンエアー(ヘッドホーン筐体から音漏れを出す構造)などは代表的な構造です。
この構造の事を話すと、色々と在るのですが、今回はダイナミック型スピーカーの基本構造説明とします。 |
